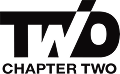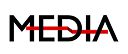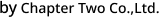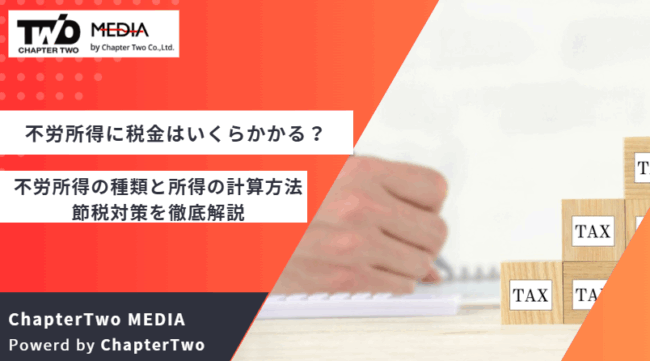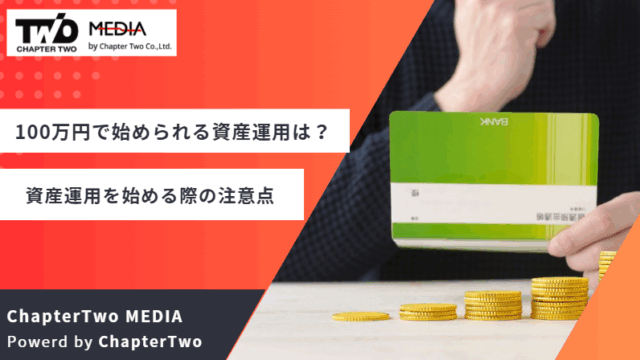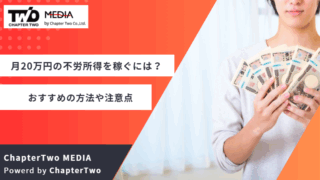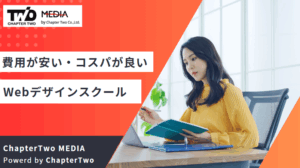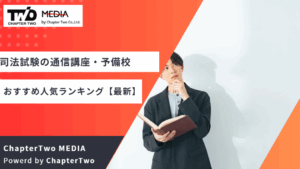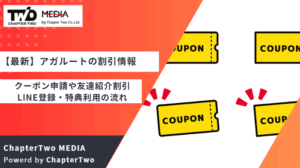不労所得に税金はいくらかかるのか、不労所得の種類と所得の計算方法について知りたい人も多いでしょう。
将来の安定的な生活の為に不労所得に注目する人が増えていますが、税金は発生するのでしょうか。
一口に不労所得といっても実はさまざまな種類があり、不労所得の種別に応じて税金の取り扱いや控除額も異なります。
不労所得を得るには、不労所得を得るための方法だけでなく、不労所得にどのような税金が課せられるのかの理解が必要です。
ちなみに、2024(令和6)年国民生活基礎調査の概況によると、1世帯当たりの不労所得を含む財産所得の平均は13.7万円です。
財産所得=所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入
税金に関する知識があやふやなまま不労所得を稼ぐと、のちのち大きなトラブルにつながりかねません。
今回は不労所得の基本的な知識や所得の種類、不労所得にかかる税金や税金の計算方法など、詳しく解説します。
不労所得には税金がかかる
不労所得で得た収入にも税金は課せられます。例えば、会社員の方が不労所得で年間20万円以上を稼ぐ場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要になります。参考:国税庁|確定申告が必要な方
また、年間の不労所得が20万円未満であっても特定の状況に該当する場合には確定申告が求められます。
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 2箇所以上から受給し、かつ少ない方の給料が20万円未満で医療費控除や寄付金控除を受けたい場合
- 自営業者の場合
これから不労所得を得ようと考えている人やすでに不労所得を得ている人は、うっかり確定申告を忘れてしまわないように注意しましょう。
税金がかかるのは「収入」そのものではなく、そこから経費などを差し引いた「所得(利益)」に対してです。
税金を計算するときには、収入と所得の違いもチェックしてください。
| 収入 | 労働の対価や家賃などとして発生した金額 |
|---|---|
| 所得 | 収入から必要経費を差し引いた金額 ※所得を元に税金を計算する |
たとえば年間120万円の家賃収入があった場合、経費(管理費・税金等) 40万円がかかっていたとすると「所得(80万円)」に対して課税されます。
不労所得が年間20万円以下でも住民税申告は必須
不労所得に対する住民税は、年間20万円以下の場合でも申告が求められます。参考:総務省|個人住民税
これは住民税が賦課課税制度に基づいているため、自己申告がなければ自治体に必要な情報が提供されないからです。
確定申告をせずに情報を提供しない場合、税務上の不正行為と見なされる場合があります。
もし不労所得が20万円を下回る場合でも、住民税の申告は確実に済ませましょう。
不労所得の種類と各税金の計算方法
記事の冒頭でも触れた通り、一口に不労所得といってもさまざまな種類があり、それぞれに税金の計算方法が違います。
自分が得た不労所得がどの種類に当たるのかを明確にして、税金を計算しましょう。
- 山林所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 利子所得
- 一時所得
- 配当所得
- 雑所得
各所得の詳細と税金の計算方法を見ていきましょう。
山林所得
山林所得とは山林を伐採して売却するか、あるいは伐採せずに立木として売却することから発生する所得です。また、狩猟や漁業権利の貸与なども対象です。参考:国税庁|No.1480 山林所得
山林所得は分離課税で、対象となるのは保有期間が5年を超える山林です。
保有期間が5年以下の山林を伐採または譲渡する場合、事業的な規模で行われる場合は事業所得として、それ以外の場合は雑所得として扱われます。
山林所得は分離課税の対象であり、特定の税率で課税されます。
山林所得を算出する式は以下の通りです。
山林所得から得られる不労所得には、最大50万円の税控除が適用されるため、納税額を減らせるのが嬉しい点です。
事業所得
事業所得は、個人や法人が事業から得た収益を指します。参考:国税庁|No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
農業や漁業、製造業、小売業などはもちろん、YouTubeやアフィリエイトビジネスなどで正式に開業届を出して運営している場合も、事業所得に含まれます。
ただし、不動産関連での収入については、不動産売買や仲介業を行っている場合は事業所得になりますが、不動産を貸し出すことで得られる収入は、後ほど詳しく解説する「不動産所得」として分類されますので注意が必要です。
事業所得は総合課税の対象となり、青色申告をしている人は事業所得から青色申告特別控除を受けられます。
事業所得の算出方法を見てみましょう。
交通費や事務所の家賃なども事業所得に関連する経費に含まれるので、節税につなげやすい所得といえます。
不動産所得
不動産所得とは不動産経営から得られる収入、具体的には貸し出された物件からの家賃収入などから得られる所得です。参考:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
建物のみならず船や航空機の貸し出し、借地権の利用権なども含まれます。不動産所得は他の所得と合わせて総合課税の対象となり、全体の所得税額が計算されます。
不動産所得の算出方法は次の通りです。
総収入金額には家賃や共益費、礼金、更新料などが含まれます。
一方経費に計上できる項目はたくさんあり、上手に扱えば節税対策も立てやすいです。
不動産所得に関連する経費として計上できるものの例を見てみましょう。
- 固定資産税
- 火災/地震保険料
- 損害保険料
- 管理費
- 広告費
- 修繕費 など
給与所得
給与所得は、個人が会社や組織から雇用されることによって得られる報酬全体を指します。これには基本給、残業手当、ボーナス、各種手当などが含まれ、労働の対価として支払われる所得です。参考:国税庁|No.1400 給与所得
給与所得は以下の計算式で求められます。
給与所得は総合課税の対象ですが、受給の度に所得税が源泉徴収される仕組みです。
他の所得がない場合は源泉徴収が最終的な納税となり、年末調整の際には実際に支払われた所得税と源泉徴収された税額の差額を調整し、最終的な所得税額を確定させます。
また、給与所得者は所得税や住民税の申告をする際に、これらの収入から「給与所得控除」と呼ばれる一定額の控除を受けられ、控除に応じて実際に課税される金額が計算されます。
給与所得控除の額は給与の額に応じて自動的に決定され、より多くの給与を受け取るほど控除額も大きいです。
利子所得
利子所得とは預金の利息、公社債の利子、各種運用信託の分配金などから得られる所得を指します。参考:国税庁|No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
利子所得については得られた収入全額が課税対象となり、別途複雑な計算をする必要はありません。
利子が支払われる際には、所得税15%と住民税5%が源泉徴収されるため通常は確定申告の必要はありません。また、復興特別所得税も所得税の2.1%が追加で徴収される点も留意する必要があります。
退職所得
退職所得とは、退職時に勤務先から受け取る退職金などの所得です。長年の勤務に対する「後払い給与」としての性質や、退職後の生活を支える資金としての側面があります。参考:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
そのため、他の所得に比べて税金が非常に安くなるよう計算されます。
退職所得控除額とは勤続年数に応じて決まる控除額です。
| 勤続20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
|---|---|
| 勤続20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
ただし、役員等の勤続年数5年以下の場合など、計算式「×2分の1」が適用されない例外があります。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得です。単に入ってきた売却金額すべてに課税されるのではなく、「売却で得た利益」に対して課税されます。参考:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
| 譲渡価額 | 資産を売った金額(収入) |
|---|---|
| 取得費 | 資産を買い入れた代金や仲介手数料、設備費などの合計額 |
| 譲渡費用 | 売るためにかかった仲介手数料や測量費、建物の取り壊し費用など |
| 特別控除額 | マイホームの売却(3,000万円特別控除)など、一定の条件を満たす場合に差し引ける金額 |
不動産の譲渡所得は、その物件を所有していた期間によって税率が大きく変わります。
| 税率 |
|
|---|---|
| 長期譲渡所得(5年超所有) | 約20%(所得税15%・住民税5%) |
| 短期譲渡所得(5年以下所有) | 約39%(所得税30%・住民税9%) |
一時所得
一時所得とは、継続的な収入源ではなく偶発的に発生する収入を指します。言い換えれば営利目的ではない一時的かつ非継続的な所得です。参考:国税庁|No.1490 一時所得
例えば、宝くじの当選金、競馬などのギャンブルの賞金、保険の満期返戻金などが一時所得に含まれます。
一時所得はその他の所得とは別に計算され、特定の控除が発生します。通常の所得とは異なり特殊な事象から得られる所得のため、税法上での扱いも特殊です。
具体的には、一時所得の金額から50万円または所得の一定割合を控除した額が課税対象となります。
配当所得
配当所得とは、株式や投資信託などの証券から得られる所得です。企業が利益を上げた場合、企業は利益の一部を株主に対して配当として分配する場合があります。参考:国税庁|No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
株式を所有している株主は、企業が定める配当の支払い日に配当を受け取り、利益を得る仕組みです。
配当の金額は企業の利益や経済状況、企業が設定した配当政策によって異なり、現金ではなく株式の形で支払われるケースもあります(株式配当)。
配当所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して所得税が計算されます。
雑所得
雑所得とは、他の所得区分に当てはまらない様々な種類の所得です。日本の所得税法において、以下のような所得が雑所得と分類されます。参考:国税庁|No.1500 雑所得
- 賞金や懸賞金
- 講演料や執筆料など一時的な仕事からの収入
- 人からの贈与や遺産以外のもらいもの
- 損害賠償金
- 賃貸不動産や駐車場など、一定の設備投資を伴わない小規模な事業からの収入
これらの収入は、特定の業務や継続的な事業活動から得られるものではなく、他のカテゴリー(給与所得、事業所得、不動産所得など)に分類されないものです。
雑所得に対しては、その年に得た収入の合計から必要経費を差し引いた額に対して所得税が課されます。
また、雑所得には総合課税の対象として、他の所得と合わせて申告する必要があります。
- 公的年金等の収入-それらの控除額
- 公的年金など以外の総収入-必要経費
- 雑所得=①+②
不労所得を得たときの税金対策
不労所得を得たときの税金対策には、青色申告特別控除や非課税制度があります。
日本の税制で用意されている制度をうまく活用し、しっかりと税金対策をしましょう。
青色申告をする
青色申告特別控除を受ければ利益から最大65万円を差し引くことができ、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料も安くなります。参考:国税庁|No.2072 青色申告特別控除
ほかに純損失の繰越控除では、利益が出すぎそうな年を狙って設備投資を行うことで、その年の税金がコントロール可能です。
通常、10万円以上のパソコンやエアコンなどは数年かけて経費にしますが、青色申告者なら30万円未満であれば購入した年に年間合計300万円まで一括で経費にできます。
事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、青色申告をしましょう。
非課税制度を活用する
資産運用の非課税制度には、新NISA(少額投資非課税制度)・iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。参考:NISAを知る:NISA特設ウェブサイト
特に新NISAは非課税期間が無期限で、配当金(不労所得)を一生涯無税で受け取り続けることが可能です。
他にも、不動産を売却して得る大きな不労所得(譲渡所得)には、数千万円単位の非課税枠があります。
| 控除額 | |
|---|---|
| マイホーム売却の3,000万円特別控除 | 家を売った際、利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引けます |
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 一定の基準を満たせば利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引けます |
日本の税制で用意されている「非課税制度」を賢く使い、税金対策を行いましょう。
法人化も考える
家賃収入や事業収益といった不労所得が大きくなってきた際は、法人化をすることで強力な税金対策になります。
個人の所得税率は、課税所得が900万円を超えると33%(住民税等含めると約43%)まで跳ね上がります。
一方、法人の実効税率は約21〜34%程度で済むため、このラインを超えそうなタイミングが検討におすすめです。
会社員の方が副業で不労所得を得ている場合は、給与と合算されて高い税率が適用されるため、早い段階で法人化をすることで収益を分けるメリットが出てきます。
不動産所得などでは認められない個人の支出でも、法人なら「事業継続に必要」と認められれば経費化でき、経費の範囲が広がるでしょう。
不労所得で稼ぐメリット
不労所得で稼ぐメリットについて、くわしい情報を紹介します。
経済的に楽になることのほか、継続して収益を得られることで精神的な余裕が生まれます。
経済的に楽になる
不労所得で生活費をカバーできると、お金に対する不安が減らせますね。給与だけに頼らず、配当、家賃、事業収益などを持つことで、不況や会社の倒産、自身の病気といった緊急事態も対応しやすいでしょう。
経済的に楽になると子供の教育費、住宅ローンの返済など、長期的な支出に対する目処が立ちやすくなります。
不労所得で得たお金を自己投資や旅行などの趣味に回すことができ、人生の楽しみも増やせることがメリットです。
継続して収益を得られる
自分が動いていない間も資産が24時間働き続けてくれることで、長期的に継続して収益を得られます。
得られた収益をさらに投資に回すことで、雪だるま式に資産を増やす仕組みを作れるでしょう。
レバレッジが大きい不動産投資を例にすると、銀行の融資などを活用して元手以上の大きな資産を動かし、効率よく収益を上げることも可能です。
生活や時間にゆとりが生まれる
不労所得を得ることで給料を得るための強制的な労働から解放されます。自分の好きな時間に起き、好きな場所で過ごすことも可能でしょう。
嫌な仕事や人間関係を無理に我慢する必要がなくなり、ストレスが激減し、生活の質(クオリティオブライフ)の向上も期待できます。
家族との団らん、趣味や好きなことへの没頭など、自分が大きな価値を感じることに時間を掛けられるようになりますね。結果として生活や時間にゆとりが生まれます。
不労所得を得るときの注意点
不労所得は魅力的な一方で、事前の準備やリスク管理を怠ると、せっかくの収益がマイナスになったり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。
確定申告にはきちんと対応する
確定申告を怠ると、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった重い罰金が課せられます。参考:国税庁|所得税の確定申告
銀行口座やマイナンバーとの紐付けにより税務署の調査能力が高まっているため、「バレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
ほかにも、所得税が20万円以下で確定申告不要な場合でも、市区町村への住民税の申告は必須なので注意しましょう。
資産が減る危険性がある
元本割れリスクや資産そのものの価値が下がるリスクをきちんと理解して、不労所得で稼ぐ仕組みを作りましょう。
株式や投資信託は、経済状況によって価格が上下します。配当金で不労所得が得られていても、株価そのものが暴落して急にマイナスになる事態もあり得ます。
不動産投資の場合は、借り手がつかなければ収益はゼロになりますが、管理費や固定資産税の支払いは続きます。
自己資金が必要
不労所得を構築する仕組みを作るためには、まとまった初期費用がかかることがほとんどです。
例えば、年利3%で月5万円の不労所得を得るには、約2,000万円の元本が必要です。自己資金が少ない状態のままでは、金利上昇や収益の悪化が進むとに破綻するリスクが高まります。
不労所得で稼ぐには、まず半年〜1年分程度の生活費を現金で確保し、余剰資金で始めるのが基本です。
悪質商材や詐欺に気をつける
「絶対に損をしない不労所得」を謳うものは、まず詐欺だと疑ってください。収入を得る手段やシステムの仕組みがどこにあるか説明できない不労所得は避けましょう。参考:金融庁|詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!
悪質な情報商材にも注意が必要です。本当に稼げる仕組みなら、わざわざ公開したり他人に売って競争相手を増やす必要はありません。
月利10%以上、年利20%超などの高い利回りで、曖昧な説明の不労所得や商材は非常に危険です。
短期間の運用・低予算は利益が出にくい
短期間で不労所得に成果を求めすぎると、無理なハイリスク投資に手を出してしまい、結果的に資産を失う危険性が高まります。
他にも、低予算で始める場合は、不労所得で稼ぐことよりも「まずは本業や副業で元本を増やすこと」を重視しましょう。
例えば、10万円を年利5%で運用しても、月々の収入はわずか約400円です。 月10万円の不労所得を目指すなら、利回り5%でも2,400万円の元本が必要です。
短期間の運用・低予算は利益が出にくいことに注意し、不労所得を得る準備を進めましょう。
不労所得を得る方法7選
実際に不労所得を得るためには、どのような方法があるのでしょうか。
今回は不労所得を得る方法の中から以下の7つを厳選し、詳しく解説します。
- 株式投資
- 投資信託
- オンライン講座の販売
- ドロップシッピング
- 不動産投資
- 不動産クラウドファンディング
- 広告収入
株式投資
株式投資とは、企業の株を保持しその企業が利益を得た際に配られる配当を収入として得る方法です。参考:一般社団法人 全国銀行協会|株式(金融商品仲介)
この配当収入は不労所得と見なされますが、企業が継続的に配当を支払う能力は経営成績に強く左右されます。
対象企業の財務状況や市場での立ち位置を理解しなければ、逆に損失を生む可能性も無視できません。
また、すべての銘柄が配当を提供しているわけではないため、投資を行う前には銘柄の配当実績をチェックしましょう。
株式の購入は通常100株単位で、初期投資としてある程度の資金が必要です。投資初心者は少額からでも参加できる「単元未満株」や、1株から購入可能な米国株を扱う証券会社なども視野に入れてください。
投資信託
投資信託は、個々の投資家から集めた資金をプロのファンドマネージャーが運用し、株式や債券に投資して得られた収益を投資家に配分する金融商品です。参考:一般社団法人投資信託協会|そもそも投資信託とは?
運用は専門家によってされるため、投資の初心者でも始めやすいです。さらに多くの異なる銘柄への投資により、一部の銘柄が価値を失っても全体のリスクを抑えられます。
得られる利益は運用の成果に左右されますが、たとえば年間3%の平均利回りを持つ投資信託に200万円を投じた場合、1年後には約206万円に増加し、差額の6万円が不労所得となります。ただし、上の計算はあくまでも簡略された計算です。
実際には手数料や税金、市場の変動などを考慮する必要があります。
さらに投資信託は基本的に長期間の投資を想定しているため、短期間の市場の波に左右されずに、長い目で資産を増やしていく意識が、不労所得を実現する鍵となります。
短期的に大きなリターンを望む場合には、投資信託は向いていません。
オンライン講座の販売
専門知識やスキルをオンラインで教え、不労所得を稼ぐ方法もあります。
リアルタイムでのライブストリーミングや、事前に録画した動画を提供するオンデマンド配信の二つの形式がありますが、不労所得を狙うにはオンデマンド配信がおすすめです。
コースを制作するのには時間がかかりますが、オンデマンド配信であれば一度動画を作成してしまえば何度でも販売できます。
自分のウェブサイトを開設し顧客を集める手段がありますが、受講者の予約や管理など、多くの管理作業が必要です。
現在ではUdemyやSchooのようなオンライン講座のプラットフォームが人気を博しているので、これらのサービスを利用するのもおすすめです。
手数料こそ発生するものの必要な機能が整っているため、効率的な運営ができます。
コースの内容も投資や語学、一般教養など多岐にわたるので、自分の得意分野や専門分野を活かしたい方におすすめです。
ドロップシッピング
ドロップシッピングは、在庫を保有せずに商品を販売するビジネス手法です。
一般的なネットショップでは商品を仕入れて在庫を持つ必要がありますが、ドロップシッピングはサプライヤーが直接顧客に商品を送るため、自らの商品を管理したり、配送したりする必要がありません。
この方式では初期投資を抑えてECサイトを開設できるため、副業としても低リスクで始めやすく、人気を博しています。
仕組みを一度構築すれば、大きな労力を要することなく持続的に収益を上げられます。一方で、ドロップシッピングは競争が激しく、価格戦争に巻き込まれやすいです。
さらに商品を直接手に取って確認できないため、使用感などを自分で把握せずに販売する難しさがあります。
不動産投資
不動産投資はアパートやマンションを購入し、賃貸することで家賃収入を得る方法です。
この投資の利点には、「家賃収入が入居者がいる限り安定して得られる」「不動産の価値や家賃の変動が株式のように大きくない」「サラリーマンの場合、税金の優遇措置を受けられる可能性がある」といった点が挙げられます。
不動産の価格変動が比較的少なく、物件の管理を専門の管理会社に委託できるため、本業がある人でも不労所得を目指しやすい投資手法です。
一方不動産投資ローンを利用して物件を購入する場合、「ローンが完済されるまで大きな利益を得にくい」「入居者がいなくなると、空室期間中は収入を得られない」というリスクもあります。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングとは、オンラインプラットフォームを通じて投資家から資金を集め、その資金で不動産を購入し運用した後、得た利益を投資家に還元する投資方法です。
投資家が直接物件を購入する必要がないため負担が少なく、投資の初心者や小額から始めたい人にもアクセスしやすいと言えます。また、利回りは年間約2%から5%であるケースが多いです。
ただし、入居者数が減少すれば家賃収入が下がり配当への影響を与える点や、クラウドファンディングを運営する事業者が経営破綻すれば、投資金が失われるなどのリスクもあります。
さらに不動産クラウドファンディングは換金性と流動性に乏しく、運用期間中の早期解約が困難な点にも注意しなければなりません。
広告収入
YouTubeやブログを用いてアフィリエイト報酬という形で広告収入を得る方法もあります。
自らが運営するYouTubeチャンネルやブログサイトで動画や記事を公開し、メディアに掲載された広告から商品が購入された際に広告主から報酬が支払われるシステムです。
多くのメディアプラットフォームは無料で利用できるので、サーバー費用など少額の初期投資でスタートできます。
収益化には相応の時間と努力が必要ですが、一度稼げるシステムを構築できれば広告主からの継続的な報酬も夢ではありません。
ただし競争が激しく、コンテンツを増やしても自サイトが検索に引っかからなければ収益が上がらない可能性も高いです。
さらに扱う商品のトレンド変動や検索エンジンのアップデートにより、定期的なメンテナンスや更新が求められる場合もあります。
不労所得と税金に関するよくある疑問を解消
不労所得と税金に関するよくある疑問の対応策や回答を詳しく解説します。
雑所得100万の税金はいくらですか?
本業の給与所得に雑所得100万円が上乗せされるため、本業の年収が高いほど税金も高くなります。
不労所得で月10万円を得るにはいくら必要ですか?
高配当株の一部や、債券などを組み合わせた安定志向の運用でも高額なお金が必要なので、必要な元手には気を付けましょう。
YouTubeで20万円以下の収益でも住民税はかかりますか?
住民税には「20万円以下なら非課税」というルールはありません。所得が発生すれば、原則として課税対象となります。
所得税と住民税では、非課税になる基準や範囲が異なるので注意しましょう。
不労所得で一番損する所得はいくらですか?
また主婦の方などが不労所得を「確定申告」した場合、所得が48万円を超えると、自身の基礎控除を使い切り、世帯の「配偶者控除」から外れる可能性があります。
無職でも不労所得に税金はかかる?
ただし、不労所得が年間48万円以下であれば、所得税はかかりません。しかし、年間所得が増えるにつれて住民税や国民健康保険料も段階的に上がっていきます。
不労所得にも原則として税金はかかる
収入の得かたに関わらず「利益」が発生すれば、「所得」として課税対象になります。所得の種類によって計算方法や税率が大きく異なるため、不労所得で稼いだらしっかり管理しましょう。
非課税制度を活用し税金対策をすれば控除対象になり、今払っている税金が安くなることがあります。
また、所得税の申告が不要な「20万円以下」であっても、住民税の申告は別途必要なケースがほとんどです。自治体によっては少額でも申告を求めているため、注意が必要です。