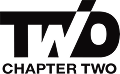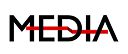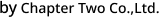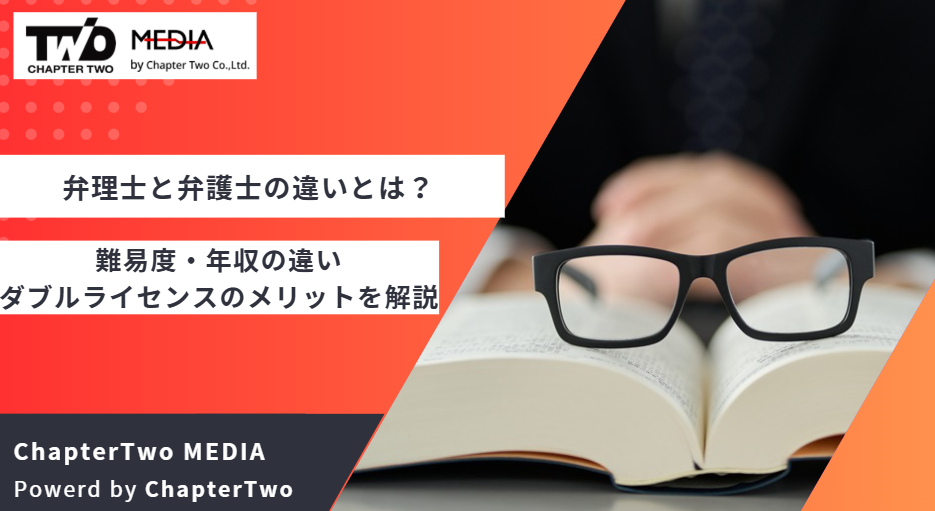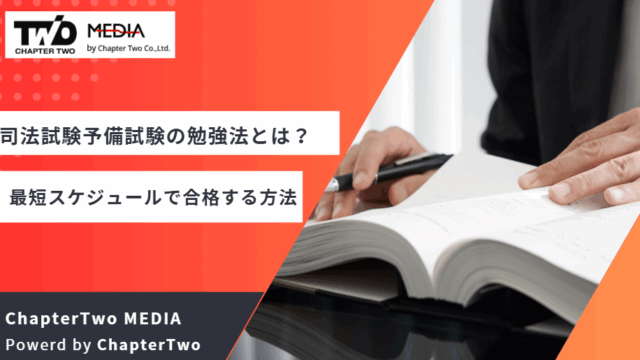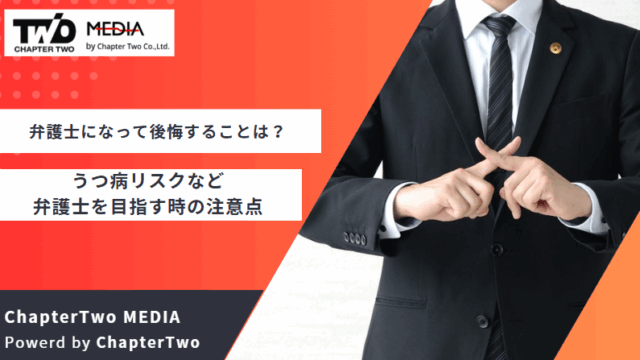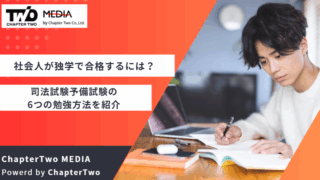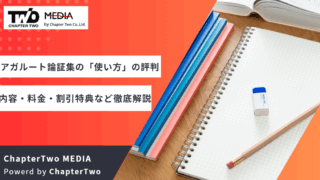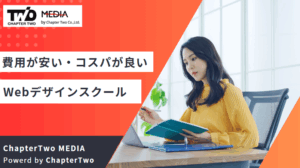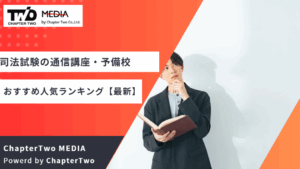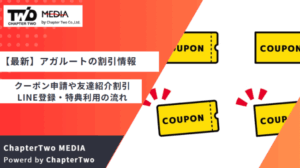”知的財産の専門家”と呼ばれている弁理士は、『商標』や『特許』『意匠』『実用新案』などの法律の知識に長けています。
それらを活かして活躍することから、個人のスキルが高ければ高収入にもつながります。
そんな弁理士の仕事は、同じく法律を扱う弁護士とどんな違いがあるのでしょうか?

弁理士の仕事内容
特許取得の申請
知的財産とは、誰かが考えたアイディアや創作物のことを指し、財産のような価値を持ったものがいくつもあり、知的財産の中には法律で守られるべきものがあり、弁理士はその知的財産を権利化するお手伝いをします。
前述した通り、弁理士は何か新しい技術や、権利を特許庁に「知的財産」の権利の申請を行っています。
これらの特許の申請がで出来るのは弁理士の独占業務となっており、「知的財産」に関する専門的な知識が必要になってきます。
新しく生まれたアイデア・技術を第三者に違法に奪われないように守り、権利化するのは社会的に大切となっており弁理士の仕事はとても重要です。
コンサル業務・取引関連業務
また、特許の申請に関して特許を取得しようとしている方にアドバイスなどのコンサルティングも行っています。
他にも自分が取得している特許を許可も無く使用された場合の訴訟などの手続きも弁理士の一部の業務となっています。
弁理士の業務範囲は日本のみならず海外の知的財産の取得や、ライセンスに関する契約などのコンサルや、仲介も行っているので弁理士が活動する範囲は広範囲に及びます。
弁理士と弁護士の違い
違い1】専門としている分野
弁理士が得意としている分野は”知的財産”に関することです。
これは新たなデザインや発明のことで、このせっかくのアイディアが誰かの手によって勝手に使われたりしないように、権利化することが必要となってきます。
権利化するために必要な出願などの手続きを、発明者に代わって特許庁へ行うのが弁理士の役割です。
では、弁護士が得意としている分野が何かと言うと”社会生活をしていく上で起こった事件などに対し、適切な対処を行って解決に向けたアドバイスをすること”です。
弁理士は知的財産を専門としていますが、弁護士は日常で起きたトラブルはすべて取り扱っているので、幅広さが全然違うことが分かりますね。
さらに弁理士と弁護士では、働くうえで求められる知識も若干違ってきます。
様々な知識が欲しいという部分は似ていますが、弁理士の場合は、発明などに関する最先端の知識が常に必要とされてきます。
弁理士には理工系出身の人が多く、弁護士には文系出身の人が多いです。
違い2】弁護士資格があれば弁理士試験は免除
弁理士資格は弁護士の資格を持っていると弁理士登録することができます。
弁理士に登録するために日本弁理士会の研修を受ける必要がありますが、試験を受ける必要がありません。
司法試験に受かって弁護士になった人で、弁理士の試験を受ける方はほとんどいませんが「知的財産権」を専門や、得意としたい方は受けることもあるようです。
弁護士を受かっていると弁理士になることは出来ますが、弁理士資格を受かっても弁護士にアドバンテージはありません。
弁理士と弁護士の給料を比較
| 項目 | 弁理士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 初任給 | 約35~40万円 | 約38万円 |
| 月給 | 約40万円 | 約64万円 |
| 年収 | 約490~645万円 | 約780~1030万円 |
弁理士と弁護士の初任給は大体同じ給料となっていますが、キャリアを積むにつれて年収に300万円以上の差が出てきます。
独立・開業した時の給料を比較
先程は企業で就職して働く際の給料に違いについて見てきましたが、弁理士や弁護士などの資格は独立、開業が可能となっているおり、当然給料や年収にも変化があります。
個人によって差はありますが、弁理士で独立・開業した場合、1,000万円以上を稼げると言われています。
弁護士が独立した場合は、もちろん個人差はありますが、1,500万円くらいが平均と言われています。
弁理士で独立することが出来た場合は弁護士と給料はあまり変わらないと言えます。
弁理士と弁護士になる難易度を比較
弁理士と弁護士(司法予備)の試験を項目別にまとめて見ました。*令和5年度参照
| 項目 | 弁理士 | 弁護士(司法予備試験) |
|---|---|---|
| 勉強時間 | 3,000時間 | 3000~10000時間 |
| 合格率 | 6.1% | 3.58% |
| 受験者数 | 3,065 人 | 1万3,372人 |
| 合格者人数 | 188 | 479人 |
弁理士と弁護士の資格の難易度を比較して見ると、勉強時間では最高で7,000時間の差があり、かなりレベルに差があることが分かります。
合格率でも見てみると、どちらも10%を切っており、難易度は高くなっていますが、弁護士(司法予備試験)は受験者数が1万人以上を越えているのに対して、合格者が約500人となっており、ほとんどの人が落ちています。
弁理士と弁護士の試験の難易度は、弁護士(司法予備試験)の方が難易度は高いと言えます。
弁理士と弁護士は業務内容が大きく異なる
知的財産に関する法律に強く、権利化に向けての手助けをしてくれる弁理士になることは、非常に難関となっており、同じ法律に携わっている弁護士とは扱っている分野に違いはありますが、時として共同で力を合わせることもあるようです。
弁理士と弁護士の試験にといて、どちらもかなり難易度が高く、複数回受験してやっと合格しているという人が多く、難易度の高さが窺えます。
しかし、弁理士は特許事務所に就職できればその収入は安定しており、また、独立して営業がうまくいけば数千万円の年収と弁護士と変わらないケースもあります。
知的財産に興味がある方は、ぜひ弁理士の資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。