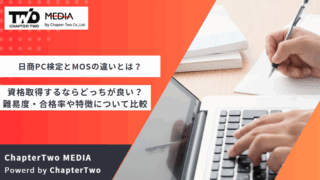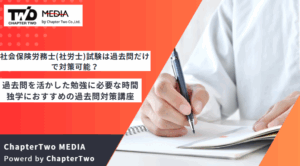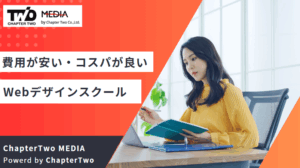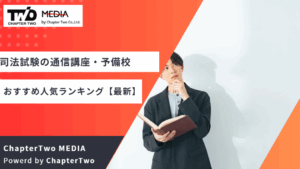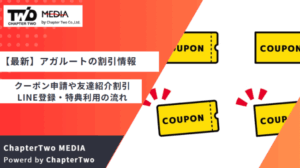「社労士試験の対策は過去問だけでいい?」
「社労士の過去問をひたすら解けば合格できる?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
結論から言うと、社労士試験に過去問だけで臨む受験生がいますが、これはおすすめできません。
そもそも社労士試験は合格率が5~8%程度の超難関資格なので、まずは時間をかけてインプットを行い、着実に知識を習得する必要があります。厚生労働省:社会保険労務士試験の結果について
過去問だけの勉強で社労士試験に合格するのは非常に難しく、現実的ではないため、テキストを活用しながらインプットとアウトプットをバランスよく行いましょう。
こちらの記事では、社労士試験の過去問だけの対策で合格するのが難しい理由や、過去問のおすすめ活用法などを解説していきます。
社労士試験合格は過去問の独学だけでは難しい
社労士試験に臨む上で、過去問演習を行うことは非常に重要ですが「過去問だけ」取り組む勉強では、残念ながら社労士試験に合格するのはかなり難しいでしょう。
前提として、テキストの読み込み、条文や判例の理解などのインプットをしてから過去問演習のアウトプットをこなすことで、知識が脳に定着します。
過去問だけでは「アウトプットのみ」の勉強になってしまうため、全体的なバランスが崩れていると言わざるを得ません。
インターネット上で「過去問だけで社労士に合格できる!」などの投稿を見つけたとしても、鵜呑みにするのは危険です。
難関試験に合格するためには、「バランスの良いインプットとアウトプット」が必須となるため、過去問だけに取り組む勉強は避けましょう。
社労士試験に過去問だけで合格するのが難しい理由
社労士試験に過去問だけで合格するのは、非常に難しいです。
基礎知識を十分に習得できない状態で過去問を解こうとしても、知識が圧倒的に不足してしまうでしょう。
過去問だけで合格するのが難しい理由について、詳しく解説していきます。
理由1】基礎知識が圧倒的に不足する
過去問を解くだけでは、社労士試験で関連する各種法令の基礎知識を十分に習得することができません。
テキストには、問題を解くために必要となる基礎知識や根拠となる条文が載っているため、テキストを読むことで着実に基礎知識を習得できます。
基礎をしっかり習得していないと応用問題に対応できないため、テキストの読み込みは非常に重要なフェーズと言えるでしょう。
つまり、テキストを読むフェーズを飛ばして過去問だけ取り組んでいても、基礎知識が圧倒的に不足してしまうのです。
過去問の問題解説は「基礎知識を習得していることを前提」としているものも少なくないため、基礎知識が不十分だと過去問演習の質が下がってしまうデメリットもあります。
| 試験科目 | 選択式 計8科目(配点) | 択一式 計7科目(配点) |
|---|---|---|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
1問(5点) | 10問(10点) |
| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
1問(5点) | 10問(10点) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題はありません。択一式の「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」は、各10問のうち問1~問7が「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」から出題され、問8~問10の3問(計6問)が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」から出題されます。
理由2】重要なポイントが分からない
テキストは重要単語や頻出分野では文字を強調するなど、重要なポイントが分かりやすいようにされています。
そのため、テキストを読まずに過去問だけで勉強を進めると、試験対策上重要なポイントが分からないまま、勉強を進めることになります。
効果的な本試験対策をするためには、頻出論点や重要分野を把握した上で、メリハリをつけて勉強することが大切です。
過去問題集でも、重要度をランク付けしている教材はあるものの、テキストと比べると情報量が劣ってしまうのは否めません。
重要なポイントを把握することで効率よく得点を稼げるようになるため、過去問だけだと非効率な勉強になってしまうでしょう。
理由3】理解力と応用力が身に付かない
過去問だけ取り組む勉強法だと、問題を解くために必要となる理解力と応用力が十分に身に付きません。
理解力と応用力は、「基礎知識があって初めて培われる」ため、テキストの読み込みを飛ばして過去問だけ取り組むと、十分な本試験対策ができないのです。
過去問に類似した問題であれば一定の対策が可能になりますが、初見の問題を解く上で基礎知識が不十分なのは致命的です。
理解力と応用力がなければ本試験の問題に対応できない可能性が高く、合格は難しくなってしまうでしょう。
理由3】根拠となる理屈が理解できない
社労士試験はさまざまな法令や判例から出題され、いずれも問題を解くための「根拠や理屈」の理解が重要です。
テキストを読み込むことで法令や判例を確認できますが、過去問を解くだけでは十分に理屈の部分を理解できません。
過去問の解説欄では、ページの都合などで細かく「理屈」を解説できないため、理屈を理解するためにはテキストの読み込みが必須です。
根拠が分からないと問題を解くためのヒントが掴めないため、テキストを読み込んでいる人と得点力に差がついてしまう可能性が高いです。
加えて、過去問だけ取り組む勉強法だと「過去問を解くための勉強」に終止してしまい、本試験で思うように得点ができずに終わってしまうでしょう。
理由4】独学は苦手分野が放置されがち
過去問を解いて間違えた問題があれば、テキストを読み直すことで正しく知識を習得する必要があります。
過去問だけ取り組んでいると、肝心な復習や見直しが十分にできないため、苦手分野が放置されがちです。
社労士試験には、各科目ごとに「足切り基準」が設けられていることから、苦手分野があると合格が難しくなってしまいます。
苦手分野をできるだけ少なくして、足切りのリスクを抑えることが社労士試験合格のカギとなりますので、過去問だけでは合格を掴み取るのは難しいと言わざるを得ません。
理由5】労一・社一の対策が難しい
社労士試験では、「社会保険に関する一般常識」「労務管理に関する一般常識」という科目が出題されます。
いずれも、最新の法改正や統計データから出題されることが多く、過去問だけでは対応するのは難しいです。
過去問は、当然のことながら「過去」に出題された問題ですから、最新の情報が出題される一般常識科目の効果的な対策にはなりません。
一般常識科目は多くの受験生が対策に苦労している鬼門の科目なので、過去問だけで挑むと足切りに引っかかってしまう可能性が高いでしょう。
理由6】足切りになる危険性がある
社労士試験には足切り基準が設定されており、基準を満たさないと全体の点数が高くても不合格になります。
合格基準点は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めます。各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)。
社労士合格に必要な正答率はおおむね6割〜7割で、過去問だけでも全体の6割を目指せますが、新問が多かったりすると足切りラインを突破するのは困難です。
年度によっては基準点が引き下げられることもありますが、原則として選択式5問中3問以上、択一式10問中4問以上の正解が求めらるので注意しましょう。
理由7】論点の正しい理解ができない
試験対策を過去問だけにすると、〇×判定の正誤だけを覚えてしまうことがあり、問題の数字が変わったり、表現が変わったりすると得点できなくなることがあります。
違った角度からの出題にも回答できるように、論点の正しい理解や応用問題への深掘りをし、うまく対策してください。
過去問の学習は、問題ごとの論点や根拠をテキストで確認し、理解を深めることをおすすめします。
しかし過去問演習をこなすことは非常に大切
過去問だけで勉強をしても、社労士試験に合格するのは難しいです。
しかし、「過去問だけ」で合格するのは難しいだけで、「過去問を解く」ことは試験に合格するためには欠かせません。
以下で、過去問演習をこなすことの重要性について解説していきます。
実際の問題のレベル感を掴める
過去問は、過去に本試験で出題された問題を掲載しています。
実際に本試験と同じレベルの問題を数多く取り組むことができる有用なツールなので、有効活用しましょう。
本試験レベルの問題に多く触れることで、本番でのレベル感を体感できます。
また、社労士試験では過去に出題した内容と似通った選択肢が出てくることもあるため、過去問を繰り返し解くことで、選択肢の正誤をスムーズに判断できるようになるでしょう。
過去問のレベルを難しく感じることなく、「過去問のレベルが当たり前」になれば、本試験の初見の問題にも冷静に対処できるはずです。
苦手分野を重点的に対策できる
多くの過去問題集は、科目ごとに問題をまとめて収録しています。
これにより、自分の苦手分野を重点的に対策できるため、効率よく得点力を鍛えることが可能です。
苦手分野の問題でも、繰り返し解いて解説を読むことで、自然と脳にインプットされます。
先述したように、社労士試験には足切り制度があるため、苦手分野が多いと合格できる可能性が低くなってしまいます。
過去問を上手に活用して、苦手分野を徹底的に潰せば、安定して得点できるようになるでしょう。
インプットとアウトプットのバランスを意識することが大切
過去問を解くことは「アウトプット」に該当しますが、まずは知識を仕入れる「インプット」を行いましょう。
テキストを読み込むなど、インプットを済ませてから過去問演習などのアウトプットを行うことで知識が定着しやすくなります。
また、インプットを完全に行う必要は無く、何回読んでも分からないような箇所は一旦放置して構いません。
実際に問題を解くことで「こういうことだったのか!」と手応えを掴めるケースは多々あるため、インプットとアウトプットはバランス良く行いましょう。
頻出論点に強くなる
社労士試験は試験への出題回数が多い「頻出論点」という問題があり、過去問を解いていくなかで理解が深められます。
頻出論点は社労士試験のなかでも得点の割合が高く、どれだけ確実に取れたかが合格に影響するのです。
頻出論点をA、過去に出た問題から派生した問題がB、難問をCとすると、CよりもAとBの問題の正答率が高いほど社労士試験に受かりやすくなります。
社労士試験の過去問は5年分を3周しよう
過去問をこなすことは非常に重要ですが、「どれくらいの量をこなせばいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
あくまでも目安にはなりますが、「過去5年分を3周」「1冊の過去問題集を3周」程度はこなしておきたいところです。
社労士試験で問われる内容は細部に及ぶため、試験で狙われる内容や出題傾向を掴むためにも、同じ問題を解くことは効果的です。
また、2周目以降に間違えた問題に関しては付箋を貼る・自分のノートにまとめるなど、同じ間違いをしないように徹底的に対策しましょう。
3周程度こなせば、本試験レベルの問題に慣れることができるので、その後は自分の苦手潰しや一般常識対策に時間を割くと良いでしょう。
過去問以外ですべき社労士試験の勉強
社労士試験の勉強で過去問以外ですべきことは、テキストを何回かきちんと読み込み、理解度を深めることです。
補足部分やテキストの細かい箇所から出題される年度も多いため、くまなく読んで完全に理解することが重要と言えます。
知識として定着させるためには、判例集や論点の参考本などもある程度の時間をかけて読むことをおすすめします。
時間が経ってしまうと、せっかく読み込んで勉強をしたことを忘れてしまう危険性があるので、学習のタイミングは十分に注意してください。
社労士試験に過去問対策だけで臨むのは難しい
社労士試験合格のために過去問対策だけで臨むのは、難しいことをお伝えしてきました。
社労士のような難関資格試験では、テキストをしっかりと読んで基礎知識を習得した上でアウトプットをこなす必要があります。
テキストを用いないと、基礎知識が圧倒的に不足してしまう上に苦手分野が放置されてしまうなど、様々なデメリットを被るため注意しましょう。
とはいえ、過去問演習は社労士試験に合格するためには必須なので、上手に活用しながら合格をつかみ取りましょう。
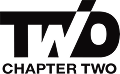
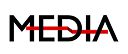
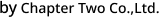
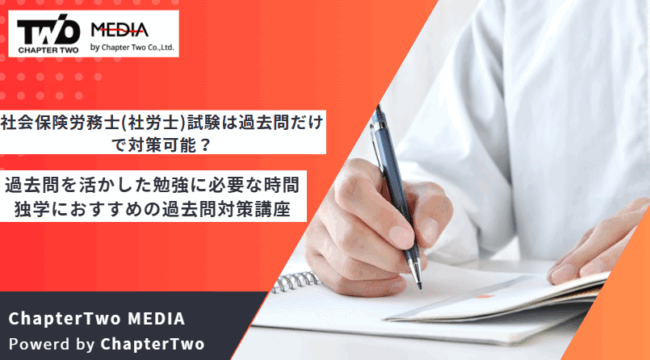
講座-e1755575471480.png)