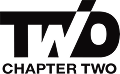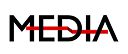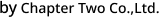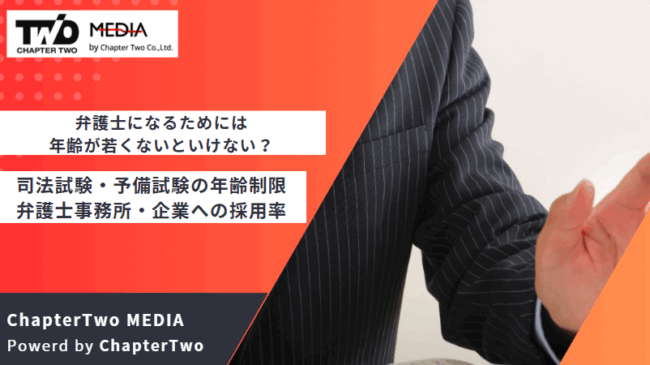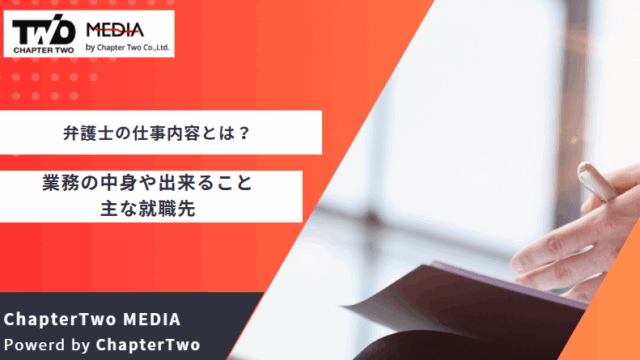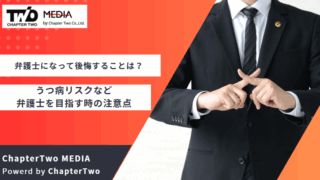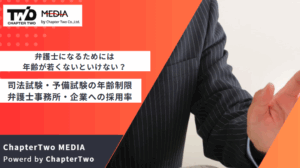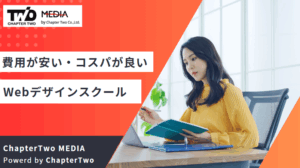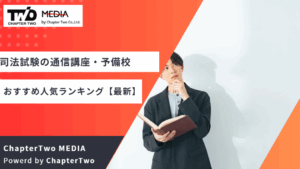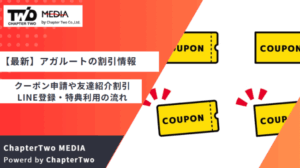弁護士は法の専門家として活躍する非常に難易度が高い仕事、資格となっています。
テレビやドラマで弁護士が活躍する姿から弁護士に憧れている方も多くいらっしゃりますよね。
弁護士資格には年齢の制限があるのでしょうか?
今回の記事では弁護士資格の仕事内容や、年齢制限、就職と年齢の関係などについて詳しく紹介して行きます。
弁護士の主な仕事内容
弁護士の仕事内容は法律相談でのアドバイス・法律関する書面の作成・裁判手続きを行うなど弁護士の仕事内容は多岐に渡ります。
裁判で活躍するイメージが強いですが、それ以外にも多くの活動を行っているようですね。
この紹介した業務内容はあくまで1部なので他にも弁護士の仕事はたくさん存在します。
やりがいの多くは困っている人を助けることが出来るというもので、弁護士は様々な環境に置かれている方々を法的視点から解決していきます。
また、弁護士は社労士・弁理士・税理士・司法書士・行政書士・海事補佐のこれらの仕事を全て行うことが出来ます。
司法試験・予備試験に年齢制限はある?
弁護士自体に年齢制限は一切ありませんが、司法試験の受験回数の制限はあります。
就職活動を考えるなら弁護士資格の取得は30代までが目安となっていますが、弁護士資格保有者の年齢層は高く30代でも若手として扱われます。
あくまで30代までが目安というまでで、30代を過ぎて取得しても遅いことはありません。
中には40代、50代で弁護士資格を取得する方も存在するので、年齢は関係ないと言えます。
弁護士の就職と年齢は関係ある?
年齢が若ければ若いほど大規模な企業や大手弁護士事務所に対しては有利に働きますが、大規模では無い中小規模の企業・弁護士事務所であればある程度歳を取っている方が就職しやすくなると言われています。
これは、一般的な企業が新卒市場で優秀な学生をポテンシャル評価でいち早く採用しようとするのに対し、弁護士事務所は一般的にそこまで組織的な団体ではなく、常に即戦力が欲しいところが多いためです。
研修等で優秀な若い新人弁護士を青田買いして成長を待つという時間的・資金的余裕が無いため、ある程度歳を取っていて、新卒の学生よりビジネスマナーを最初から知っている、、という方を中小の弁護士事務所などが求めることもあります。
ただし、大手事務所の中でも、特に新卒学生を優遇するといったことをせず、ビジネスマナーや過去の実績なども含めて評価した結果、基本的には新卒や20代前半で入所が難しくなっているところはあります。
弁護士になる年齢が若い=優秀さとして扱われることも多い
予備試験・司法試験は日本でもトップの難易度を誇る国家試験ということで、いかに早く合格したかや、上位何位の得点で合格したかなどは、弁護士としてのキャリアの強みにもなります。
古くから、予備試験や司法試験をいかに若くして合格したかは弁護士の優秀さを測る指標にもなっているため、弁護士として評価されるためには若くして予備試験・司法試験に合格するに越したことはありません。
ただし前述の通り、入所希望者の若さは比較的評価をしない大手弁護士事務所も多いため、予備試験・司法試験合格が遅いことがキャリアでマイナスになるとは一概に言えません。
基本的には年齢が高いことは大きなマイナスにはならない
前述の通り、若くして予備試験・司法試験に合格したことで外へアピールできたり、採用時に評価されたりするケースは少なからずあります。
ただし、このことはほとんどの方にとって大きな問題ではありません。なぜなら予備試験・司法試験は日本最難関の試験であり、たくさんの新人弁護士が1年で生まれる訳ではありません。
加えて、一部の大手弁護士事務所を除いて毎年、安定した求人への募集が集まる訳でもありません。
このような弁護士人材の需要と供給のバランスを考えると、例えば一般企業の中途採用などのように、年齢が高いことは市場でマイナス評価となるとは必ずしも言えないのです。
年齢がある程度高い弁護士の方が優遇・評価されるケース
前述の通り、予備試験・司法試験に合格するには年齢が若いほうが良いということはありません。
また、一般企業への就職と比べて、年齢が高いことが弁護士事務所の採用面接などでマイナスに働くということもそこまで多くありません。
下記のようなケースでは、年齢がある程度高い方の方が優遇されることもあります。
ケース1】ビジネスマナーやポータブルスキルが備わっている
弁護士のような専門職でも挨拶や身だしなみ、礼儀などのビジネスマナーや論理的思考力、文書作成能力などのポータブルスキルは重要です。
大学を卒業したてよりも過去に社会人経験のある弁護士の方が、こうしたスキルは最初から備わっている可能性が高いです。
ケース2】これまでの経験で培ったスキル・知見がある
学生時代をほとんど司法試験の勉強に費やした方よりも社会人経験や、法律とは違う勉強をしたことなどが事務所採用で評価されたり、弁護士として活躍する上で大きな武器になったりすることがあります。
例を挙げると近年増えてきたフリーランスと企業間での契約の問題や、IT・Web領域の問題、AIによる著作権侵害などは、実際にフリーランスで働いた経験や、エンジニア・AI領域に詳しい方の方が取り組みやすいでしょう。
ケース3】持っている人脈が弁護士業務に繋がりやすい
前述の通り、弁護士事務所はチームとして業務を進めるケースはそこまで多くなく、各自が個別に案件を取ってこないといけないことも多いです。
この際、大学を卒業してすぐに弁護士になった方よりも、法曹以外での経験を経て弁護士になった方の方が、こうした人脈を形成しており、相談依頼を受けやすい状況にあることも少なくありません。
ケース4】弁護士として優秀と判断される
こちらも前述の通り、毎年どのような新人弁護士が弁護士事務所や企業へ応募に来るかは、予備試験・司法試験の難易度が非常に高いため、必ずしも大まかに決まった傾向がある訳ではありません。
そのため、年齢が高かったとしても優秀さが認められるのであれば、特に年齢は関係なく採用される可能性が十分あります。
年齢の高い新人弁護士は最初から独立するのも一つの手
弁護士事務所へ入所する新人弁護士の多くは、まず実務を覚えた上で、独立をして自身の事務所を持つことを目標としています。
社会人経験が長かった方などは、その経験を活かして最初から自身の弁護士事務所を構えるというのも一つの手です。
ただし、弁護士に限らず法人経営は簡単ではなく、常に失敗する可能性があります。
失敗した場合のリスクヘッジはどうするのかについても、しっかりと考えておく必要があります。