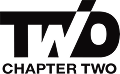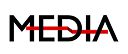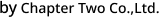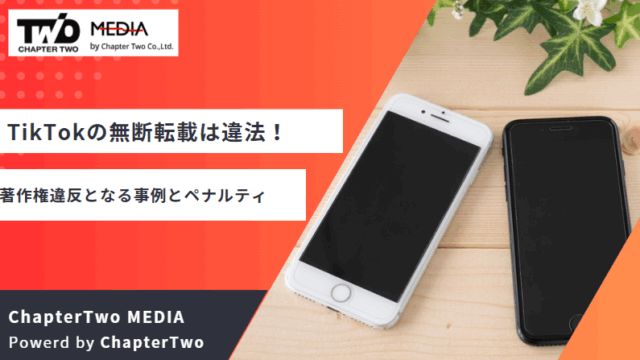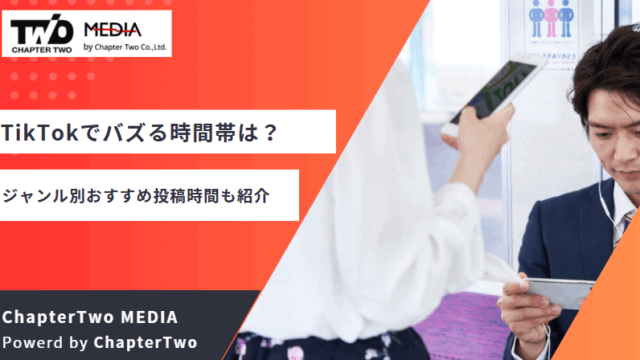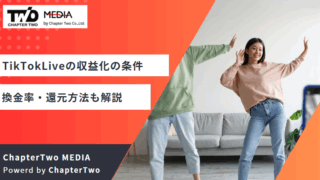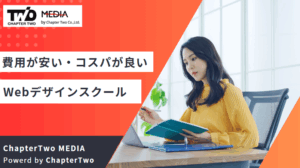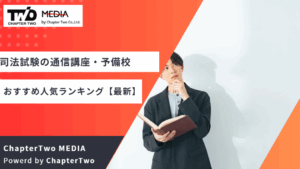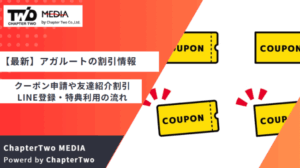TikTokはZ世代を中心に圧倒的な支持を集める動画プラットフォームとして定着し、企業によるマーケティング活用も急速に進んでいます。
従来のSNSと異なり、拡散力や動画ならではの訴求力に優れており、認知拡大・ブランディング・商品理解促進など多角的な効果が期待されています。
本記事では企業がTikTokをどのように活用すべきかについて、アカウント運用・コンテンツ戦略・広告の活用・事例分析・リスク対策まで、具体的かつ実践的に解説します。
費用が安い動画編集スクール・講座おすすめランキング19選!完全オンラインでコスパよく学べる人気スクールを徹底比較【初心者・副業・資格・転職にもおすすめ】
| 受講料 | 動画編集ツール |
|---|---|
| 分割料金 月々8,933円~ | 3ヵ月分実質無料(After Effects・Premiere Pro含む) |
| 体験講座 | サポート内容(卒業後も含む) |
| カウンセリング参加者全員 無料受講可能 | 個別質問無制限/営業同伴/専用サロン/卒業生限定チャット/税金・法律・確定申告の方法など |
-
案件獲得率:97%※2022年10月 受講生アンケート結果
- 受講満足度:95%※2023年1月 受講生アンケート結果
- 卒業後も専属メンターが無期限サポート
企業がTikTokを活用するメリット
メリット1】若年層ユーザーへの高い訴求力がある
TikTokは10代・20代のユーザー比率が高く、企業にとっては若年層へのブランド認知や商品理解を深めるための有力なチャネルです。
特にテレビ離れや検索エンジン離れが進む中で、若年層が自ら能動的にコンテンツへ接触する数少ない媒体として注目されています。
たとえば新商品の告知やキャンペーン情報も、TikTok動画として世界観を持たせて発信することで、広告ではなく「面白いコンテンツ」として自然に受け入れられやすくなります。
実際に、TikTok発のバズがニュースやTwitterなど他媒体に波及し、マスメディア級の影響力を持つことも少なくありません。
メリット2】バズによる拡散と高いエンゲージメントが見込める
TikTokのアルゴリズムはフォロワー数に関係なく「コンテンツの質」や「初動の反応」によって表示回数が左右される仕組みとなっており、企業アカウントでも短期間で大規模なバズを生み出す可能性があります。
動画が「おすすめ」に載れば、一夜で数十万再生以上されることも珍しくありません。
また、TikTokではコメント・保存・シェアといったユーザーのリアクションが活発で、企業がユーザーと直接的な接点を持つ機会も豊富です。
双方向のコミュニケーションが生まれることでブランドへの好感や親近感を育むことができ、ファン化・リピート購入にもつながりやすい点が特徴です。
メリット3】広告感が強くない自然なプロモーションが可能
TikTokでは広告感の強い投稿よりもユーザーの共感を得られる自然体のコンテンツが好まれる傾向があります。
自社商品の魅力を押し出すのではなく、「使ってみた」「実際の場面で活用してみた」といったストーリー性のある動画として発信することで、視聴者の心をつかむことが可能です。
たとえば化粧品メーカーであれば「朝のルーティン」「メイクの裏技」といった動画の中に商品を登場させる形が効果的で、押しつけ感のない自然なPRになります。
インフルエンサーとのコラボ投稿を活用すれば、さらに視聴者との距離感が近づき購買行動に直結しやすくなります。
TikTok企業アカウント運用の流れ【3ステップ】
企業がTikTokを活用するにあたっては、いきなり動画投稿を始めるのではなく目的の整理からコンセプト設計、運用体制の構築まで段階的なステップを踏むことが重要です。
TikTokは単なるSNSではなく、エンタメ性と拡散性を併せ持つ動画プラットフォームであるため、戦略的なアカウント運用が成果の分かれ目となります。
以下では、TikTok企業アカウント運用における基本的な流れを3つのステップに分けて解説します。
Step1】目的を明確にしてKPI設定をする
TikTokアカウントを開設する前に、まず「なぜTikTokを活用するのか」という目的を明確にすることが重要です。
たとえば、「若年層への認知拡大」「採用広報」「自社ECへの送客」など、目的によってコンテンツの方向性や投稿のトーンも大きく変わります。
目的が定まったら、次にその達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。
KPIの例としては、「フォロワー数の増加」「1投稿あたりの平均再生回数」「リンク経由のサイト流入数」などが挙げられます。
定量的な指標をもとに運用成果を評価・改善していくことが、長期的な成功に不可欠です。
Step2】ターゲットとコンセプトを設計する
TikTokで成果を出すには、誰に向けたアカウントなのかを明確に定めたうえで投稿全体の世界観やトーンを統一することが重要です。
たとえば「Z世代の女性に商品を知ってもらいたい」のであれば流行の音源やフィルターを活用し、テンポ感のある映像表現が効果的です。
また、TikTokではブランディングの軸となる“企画コンセプト”を明確にすることも求められます。
Step3】投稿ルールと運用体制の整備をする
TikTokアカウントを継続的に運用するには、属人的な運用に頼らず一定のルールと体制を整えることが不可欠です。
投稿頻度・動画尺・テロップやBGMの使い方など、フォーマットの指針を設けることでアカウント全体の統一感と制作効率を高められます。
また、動画の企画・撮影・編集・投稿・分析といった一連の作業フローを分担し、社内チームまたは外部パートナーと連携できる体制を構築することが望ましいです。
特に企業アカウントでは、炎上リスクやブランド毀損の懸念もあるため、投稿前のチェック体制やガイドライン整備も必須となります。
TikTokの活用で得られる効果【具体的なKPI】
効果1】短期間での認知拡大(関連するSNSでのつぶやき増加など)
TikTokではフォロワー数に関係なく動画が「おすすめ」欄に表示される可能性があるため、初投稿でも一気に数万回再生されることがあります。
アルゴリズムがユーザーの反応を重視してコンテンツを拡散させる仕組みのため、魅力的な動画であれば短期間で爆発的に認知が広がります。
この拡散性を活かし、サービスローンチやキャンペーンのタイミングで戦略的に活用すれば、他のSNSやWeb広告よりも少ないコストで認知拡大を実現できます。
特に若年層やZ世代向けのプロダクトにおいては、高い費用対効果が期待されます。
効果2】売上・応募数の増加
TikTokでバズを生み出すことで商品・サービスの購買や問い合わせ、採用応募といった直接的なアクションにつながるケースも増えています。
特にEC系商材や美容・飲食・アパレル分野では、「TikTokきっかけで購入した」というユーザーの声がSNSでも多く見られます。
また、採用広報の一環としてTikTokを活用する企業も増加中です。
社風や職場の雰囲気を動画で発信することで応募者とのミスマッチを減らしながら、母集団の拡大に成功した例もあります。
認知→共感→行動という導線を自然に作れる点が、TikTokの強みといえます。
効果3】ブランディング・共感形成
TikTokは短尺動画ならではのテンポ感やトレンド感を活かしながら、ブランドの世界観や企業の価値観を視覚的に伝えるのに適しています。
公式アカウントで社員の素顔や制作過程、オフショットなどを発信することで、企業の「中の人」が見えるようになり、ユーザーとの心理的距離が縮まります。
とくにZ世代は広告らしさの強いコンテンツよりも「リアルで等身大の情報」に共感する傾向が強いため、商品紹介とブランディングを両立させた投稿が効果的です。
中長期的な企業イメージの構築にもつながるため単発的なプロモーションだけでなく、継続的な発信が求められます。
TikTokを活用すべき企業・業界の特徴
TikTokはすべての企業にとって万能なSNSではなく、特に相性の良い業界や商材があります。
ユーザー層の中心である10代〜30代前半の若年層をターゲットとした商品・サービスを提供している企業は、TikTokによる集客・販促との親和性が高いといえます。
また、見た目や雰囲気で直感的に訴求できる商材・サービス、あるいはストーリー性をもたせやすい業種(例:美容・アパレル・飲食・エンタメ・教育・採用など)では、動画による影響力を効果的に発揮できます。
特徴1】若年層向けサービスを展開している企業
TikTokの主要ユーザーは10代〜20代を中心とした若年層です。
そのため、学生・若手社会人向けの商品やサービスを提供している企業はTikTokを通じたアプローチが特に有効です。
たとえば、コスメ・ファッション・学習サービス・スマホアプリなどは実際に多くの企業がTikTokでのプロモーションに成功しています。
こうした層はテレビCMやWeb広告よりもSNS経由で情報収集を行う傾向が強く、「TikTokで話題になっている」という情報が意思決定に直結するケースも少なくありません。
特徴2】視覚・エンタメ訴求がしやすい商材
TikTokは動画による視覚的な訴求に特化したプラットフォームであるため、見た目のインパクトや使用シーンが想像しやすい商材との相性が抜群です。
たとえば、料理・コスメ・ヘアスタイル・ガジェットなどはビジュアルで直感的に魅力を伝えることができ、ユーザーの関心を引きやすくなります。
また、製品の使い方や変化のビフォーアフターを短尺で紹介することで、エンタメ性と実用性を兼ね備えたコンテンツとして拡散が期待できます。
単なるスペック紹介よりも「映える」「真似したくなる」動画づくりが重要です。
特徴3】ストーリー性・人間味のあるコンテンツが作れる業種
TikTokでは「誰が」「どんな想いで」「どう作っているのか」といった背景やストーリーに共感が集まりやすいため、個人やスタッフの姿を前面に出せる業種では効果的な発信が可能です。
たとえば、飲食店の厨房風景、美容師の施術ビフォーアフター、接客業の日常などは、リアルな臨場感と親近感を演出できます。
特に中小企業や個人事業主の場合、大手との差別化ポイントとして「人となり」や「想い」を発信できる点がTikTokの強みです。
または、転職エージェントや副業目的のスクール事業など、「人生を変えたい」と思った方が利用するサービスなどは動画のコンセプトやストーリーを設定しやすいです。
TikTok企業アカウントの主なタイプ
タイプ1】商品・サービスの認知拡大に活用する
TikTokの最大の強みは、興味関心ベースでコンテンツが広がるレコメンド機能(For Youフィード)によりフォロワー以外の潜在層にもリーチしやすい点です。
そのため、企業がTikTokアカウントを運用することで、従来の広告やSNSでは接点を持てなかった層に自社商品・サービスを届けることが可能です。
特に「使ってみた」「試してみた」などのUGC的な要素を含む動画は拡散されやすく、ユーザーの自然な関心を喚起します。
加えて、バズ動画によって一気にブランド名が認知されるケースもあり、広告費をかけずに認知を広げる手段として注目されています。
タイプ2】社員が登場するエンタメ系動画で企業のファンを増やす
TikTokでは、広告色を抑えた“企業の日常”や“スタッフの素顔”を見せる動画によって、企業やブランドに対する好意的な印象を築きやすくなります。
たとえば工場の製造過程を紹介する動画や社員が登場するユーモラスな投稿は、ブランドの親しみやすさや誠実さといったイメージを自然に伝える手段として有効です。
また、エンタメ性やストーリー性を重視するTikTokの文化に合わせてブランドを表現することで従来とは異なる角度からのブランディングが可能になります。
とくに若年層ユーザーに対しては、テレビCMよりもTikTok上の動画の方が「印象に残る」「親近感がある」と感じられやすくなっています。
タイプ3】採用活動・会社の雰囲気発信
TikTokは若年層ユーザーが多く、Z世代をターゲットとする採用活動においても有効なプラットフォームです。
社員の日常や仕事風景、社内イベント、職場の空気感を動画で発信することで、「働く姿がイメージしやすい企業」として認識されやすくなります。
とくに近年は、求人票だけでなくSNSで企業カルチャーを知ってから応募を検討する学生や若手社会人が増加しています。
そのためTikTok上で企業の雰囲気を伝える動画を発信することで、ミスマッチのない母集団形成やエンゲージメント向上につながると考えられます。
TikTokで成果を出す企業アカウントの特徴
特徴1】企業・アカウントの立ち位置を理解している
特に大手企業であれば、アカウントに企業名が入ることでユーザーからも特定のイメージで見られてしまいます。
例えば激務のイメージの企業や直近で不祥事が明るみになった企業が、イメージと真逆の投稿をしても批判的な目にあいやすいです。
例えば、一般的にお堅いイメージの企業が「うちは堅いって言われるけど、実は○○なんです!」といった投稿をすると、人気が集まりやすいです。
特徴2】ユーザー目線に立っている
TikTokで成果を上げている企業は、「自社が伝えたいこと」よりも「ユーザーが楽しめる・共感できる内容」を優先しています。
広告色の強い動画や一方的な告知型コンテンツは敬遠されやすいため、ユーザーが「自然に最後まで見たくなる」演出や構成が重視されています。
具体的には、ストーリー性のある企画や、実際の利用シーンを見せる“あるある”形式、トレンド音源やエフェクトを取り入れた演出などが有効です。
視聴者のコメントやリアクションを活かして継続的に企画を発展させていく姿勢も、TikTokにおいては好反応を得やすくなります。
特徴3】TikTok特有のアルゴリズムへの理解
TikTokの拡散力は「フォロワー数」よりも「投稿動画の初動の反応」に大きく左右されます。
特に、動画公開後の数時間における視聴完了率・いいね・コメント・保存数などがレコメンド対象に乗るかどうかの判断基準になります。
成果を出している企業アカウントはこの特性を理解した上で、1本ごとの動画に対して「最初の数秒で惹きつけるフック」「コメントを促す構成」「繰り返し見たくなる展開」などを意識して設計しています。
また、週に複数本投稿してPDCAを高速で回す運用もTikTokにおいては効果的です。
特徴4】ブランドとトレンドの掛け合わせ
TikTokではトレンドの音源やハッシュタグ、企画に乗ることで再生数を伸ばしやすくなりますが、ただの“便乗”では企業アカウントとしての意味を持ちません。
成功している企業は、自社ブランドやサービスの世界観を崩さずに、うまくトレンドと融合させています。
たとえば、音源のリズムに合わせて商品特徴を紹介する、人気フォーマットを自社向けにアレンジする、ユーモアとブランディングを両立させるなどの工夫が挙げられます。
重要なのは、「トレンドを利用しながらも、見た人に企業や商品への興味を持ってもらえるかどうか」という視点です。
特徴5】オリジナリティのあるシリーズ展開
TikTokでは「このアカウントといえば○○」という認知を得ることで、視聴者の記憶に残りやすくなります。
単発で終わる動画ではなく、テーマやフォーマットを固定したシリーズ動画を投稿することで、アカウントの軸が明確になります。
たとえば、ある企業は「中の人の日常」「新人研修シリーズ」「○○を3行で解説」など、独自の切り口でシリーズ展開を行い、継続視聴を促しています。
TikTokのアルゴリズム上、過去の動画が突然バズることもあるため、シリーズ化によって一貫性を持たせる戦略は非常に有効です。
企業アカウントはコンプライアンスの観点からも極端な企画を打てず、差別化しにくいからこそ、工夫が必要です。
TikTok運用の成果を最大化するコツ
TikTokをビジネス活用する際、単に動画を投稿するだけでは持続的な成果にはつながりません。
プラットフォームの特性を踏まえた上で、戦略的な運用が不可欠です。特に企業アカウントでは、「発見される仕組み」と「目的と手段の整合性」を意識した取り組みが求められます。
ここではTikTokで継続的に成果を出すためのポイントを紹介します。
コツ1】データ分析とPDCAを徹底する
TikTokはアルゴリズムの影響を大きく受けるプラットフォームであり、過去の投稿の反応を踏まえた改善サイクル(PDCA)が極めて重要です。
TikTokの「アナリティクス機能」を活用することで、以下のようなデータが確認できます。
- 視聴完了率やリーチ数
- 流入元(フォロワー/おすすめ/検索など)
- 視聴ユーザーの属性やアクション(いいね・シェア等)
これらのデータをもとに「離脱が多い箇所の改善」「投稿時間や頻度の見直し」などを行うことで、より多くのユーザーにリーチしやすくなります。
特に視聴完了率はおすすめ欄での拡散に直結する重要指標です。
コツ2】トレンドの活用や投稿タイミングの設計をおこなう
TikTokでは、トレンドに乗ることが初動の拡散力を高めるうえで非常に効果的です。
特に「音源」「ハッシュタグ」「フォーマット(テンプレ動画構成)」など、プラットフォーム内で流行している要素を適切に取り入れることで、アルゴリズムによる露出増加が見込めます。
ただし、トレンドの寿命は短く、タイミングを逃すと一気に効果が薄れます。
そのため企業アカウントでは、日々の情報収集とスピード感ある企画・撮影体制が重要です。
また、ターゲット層のアクティブ時間帯に投稿することもインプレッションを伸ばすうえで有効です。
実際に、平日の18時~22時・土日午前などはエンゲージメントが高まりやすい傾向があります。
コツ3】目的に応じたKPI設計と運用をおこなう
企業がTikTokを活用する際は「認知拡大」「採用広報」「購買誘導」など目的に応じたKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。
目的によって重視すべき指標は大きく異なります。
- 認知拡大:再生数・リーチ数・いいね数
- 採用広報:エンゲージメント率・フォロワー数・保存数
- 購買誘導:リンククリック数・コンバージョン数・遷移率
これらのKPIを明確に定め、定期的に分析・改善を行うことで施策の成果が見えやすくなり、社内での説得力ある報告やPDCAサイクルの推進にもつながります。
なお、TikTokは「直接購入」よりも「間接的な行動喚起(興味喚起→検索→購入)」が多いため、Google AnalyticsやSNS流入計測ツールとの連携も視野に入れることが推奨されます。
TikTok活用を成功させる企業事例
TikTokの企業活用では戦略的な運用により実際に成果を上げている企業も多く存在します。
ここでは、業界別に代表的な成功事例を紹介し、どのようなアプローチが功を奏しているのかを見ていきます。
無印良品
@muji_jp SNSで話題のアイテム 4選 ※ネットストアでは、一部在庫切れが発生しております。お求めの際はお近くの店舗をご利用ください ※価格は2025年7月4日現在のものです #無印良品 #MUJI #SNSで話題 #名品 #人気商品 #チョコミントアイス #チョコミント ♬ オリジナル楽曲 – MUJI無印良品
無印良品はTikTok上で自社商品の使い方や収納術などの「Howto型コンテンツ」を中心に発信し、ユーザーの理解と共感を高める運用を行っています。
たとえば「〇〇を使った収納術」や「このアイテムの便利な使い方」など、実生活に即した内容を15〜30秒程度の動画でわかりやすく紹介。
実用性と親しみやすさを両立した発信が評価され、フォロワー数やエンゲージメントの向上につながっています。
また、コメント欄では「買ってみたい」「この発想はなかった」といったユーザーの声が多く見られ、購買意欲の喚起や自社ファンの醸成にも成功しています。
GU
@gu_official♬ I’m Falling In Love – Wildflowers
GUはTikTok上でユーザーによる投稿(UGC:User Generated Content)を積極的に活用したキャンペーン型のプロモーションを展開しています。
代表的なのが、指定のハッシュタグを使ってコーディネートを投稿してもらう形式の施策。
一般ユーザーの投稿を通じて商品の魅力を拡散し、購買や店舗来店につなげる導線を構築しています。
また、人気インフルエンサーとのコラボやトレンド音源を活用することで自社発信とユーザー発信の連動性を高める運用に成功しており、TikTokの特性を活かしたプロモーション事例の代表格となっています。
企業がTikTokを運用する際の注意点
TikTokは拡散力が高く魅力的なプラットフォームですが、企業アカウントとして活用する際には注意すべきポイントも存在します。
以下では、戦略的な運用を行ううえで特に重要となる3つの観点を解説します。
注意点1】炎上リスクに注意する
TikTokは拡散性が高いため、不適切な表現や差別的な内容が一気に炎上に発展する可能性があります。
企業アカウントでは特に、ブランドイメージを損なう投稿は大きなダメージとなりかねません。
TikTok独自の「コミュニティガイドライン」や「広告ポリシー」に加えて、自社のコンプライアンスポリシーも反映した運用ルールの整備が必要です。
また、投稿前には必ずダブルチェック体制をとるなど、内部管理も徹底することが求められます。
注意点2】成果が出る・認知が集まるまでに時間がかかる
TikTokでは投稿直後にすぐバズるとは限らず、継続的な運用と改善が不可欠です。
アルゴリズムによって徐々に再生数が伸びるケースや、一定期間後に再評価されて拡散されるケースも少なくありません。
企業アカウントの場合、一定の方向性や世界観を構築しながら、中長期的な視点で認知・ファン獲得を目指すことが重要です。
初期段階ではフォロワーや再生数が伸び悩むことも多いため、社内の理解と根気強い継続が求められます。
注意点3】TikTokでバズる型や文化を意識する
TikTokでは有名人を起用したり、とにかくお金をかけた動画を制作したりすることが、必ずしも成果に繋がる訳ではありません。
TikTokには独特の型や文化があり、分析が甘いと全く動画が伸びないということも多々あります。
企業のSNS担当としてデジタルネイティブ層を起用したり、外部のスペシャリストに依頼したりするのも一つの手です。
企業アカウントでありがちな失敗と対策
企業がTikTokを活用する際には、いくつかの典型的な失敗パターンがあります。
これらの落とし穴を事前に把握し、適切な対策を講じることが、安定的な成果につながる運用に不可欠です。
ここでは、特に多く見られる3つの失敗例とその対策を紹介します。
失敗例1】広告色が強すぎて離脱される
TikTokユーザーはエンタメ性や自然な流れを重視する傾向が強いため、あからさまな商品訴求や「広告っぽさ」が強い動画は、再生中にスキップされやすくなります。
企業側の意図を前面に押し出しすぎると、ユーザーとの心理的距離が広がってしまいます。
この対策としては、商品やサービスの魅力を“文脈の中で自然に伝える構成”を意識することが重要です。
たとえば、商品を使ったビフォーアフターや、社員によるリアルな利用シーンの紹介、生活の一コマに溶け込んだ紹介などが効果的です。
あくまで「共感」や「おもしろさ」の中にプロダクトを紛れ込ませる姿勢が、ユーザーからの拒否感を減らすポイントです。
失敗例2】流行に乗れず伸びない
TikTokではトレンドの変化が非常に早く、投稿内容が流行から外れていると再生数が伸びづらくなる傾向があります。
企業が独自の視点で動画を作成しても、ユーザーの興味関心とズレていれば見向きされません。
この問題を防ぐにはプラットフォーム内でのトレンド(音源、ハッシュタグ、フォーマットなど)を常に把握し、柔軟に取り入れる姿勢が求められます。
公式アカウントであっても「遊び心」や「ノリの良さ」を取り入れることで、再生数やエンゲージメントが高まりやすくなります。
なお、トレンドを追いかけるだけでなく、自社の世界観やブランドトーンに合ったものを選ぶバランス感覚も重要です。
失敗例3】投稿が継続できずアカウントが止まる
TikTokでは継続的な投稿が重要ですが、企業アカウントでは運用リソースの不足や成果が見えにくいことを理由に、途中で投稿が止まるケースが多く見られます。
更新が止まることで、フォロワーの離脱やアルゴリズム上の露出減少にもつながり、アカウントの価値が下がってしまいます。
対策としては、あらかじめ投稿スケジュールやネタのストックを用意しておくとともに、社内での役割分担や外部委託なども検討することが有効です。
また、初期段階では完璧な動画を目指すのではなく、短くても定期的に更新できる体制づくりが優先されます。
TikTok企業アカウント運用で成果を出すには試行錯誤が必要
TikTokは、商品・サービスの認知拡大や新規顧客層との接点づくりに有効なSNSですが、企業が成果を上げるには戦略的な設計と継続的な改善が欠かせません。
初期の方向性づくりや効果検証のノウハウに不安がある場合は、実績のある運用代行会社やTikTok専門の制作会社と連携することも有効です。
限られたリソースのなかで最短距離で成果を出すには、外部の専門性を活用する視点も欠かせません。