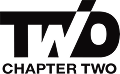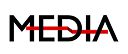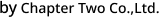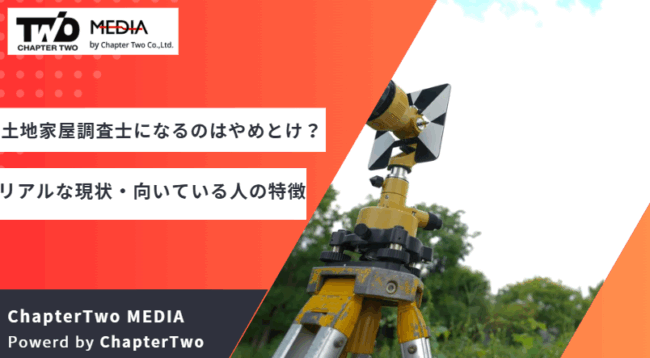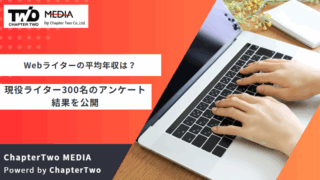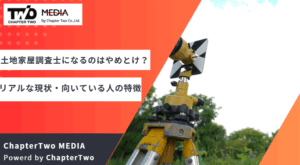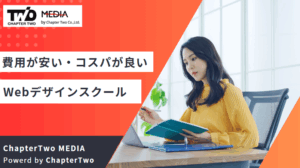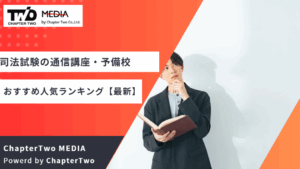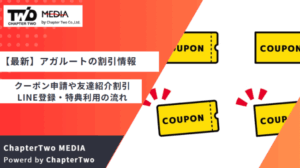近年の資格取得ブームの中でも注目を浴びているのが、不動産系資格でも最高レベルの難易度を誇る土地家屋調査士です。
「独立開業がしやすい」「収入アップが狙える」といった声も聞こえる一方で、「土地家屋調査士はやめとけ」といった意見も目にします。
今回はその声の真偽を探るべく、土地家屋調査士として働いていくことの実態を調査してきました。
土地家屋調査士になるのはやめとけと言われる理由
理由1】屋外での作業が多すぎる
同じ8士業の弁護士などはオフィスで仕事をしている様子を簡単にイメージできますが、土地家屋調査士はどうでしょうか。
1日のスケジュールの内でも外回りや計測を行っている時間も長く、「体力がないとすぐに疲れる」「肌が弱いからすぐに痛くなる」といった声は少なくありません。
また免許を持っているだけではなく日常で運転するレベルの腕前が求められるのも、都心部にお住まいの方にとってはハードルかもしれません。
理由2】土日祝日の業務が多い
土地家屋調査士は家と家の土地の境界を確かめるのも大切な業務ですが、主に土日に行われることが多いことから休日出勤が常態化しています。
仮に業務がなかったとしても関連業者から電話がかかってくる事も多く、完全にプライベートを確保したい方には辛い環境と言えるでしょう。
依頼主が平日仕事をしているため仕方ないのですが、これには誰もが不満を感じるはずです。
理由3】繁忙期が非常に忙しい
一般的な会社員の「繁忙期」と土地家屋調査士の「繁忙期」には、実はかなりの違いがあるのです。
土地家屋調査士の大型案件は数百万円と規模が大きく、時期によってはそれが何個も同時並行で進めなければなりません。
もちろん所属する事務所にもよりますが、時期によっては早朝から深夜にわたる勤務があると覚悟する方が多いようです。
理由4】人間関係のトラブルが多い
業務で隣地を訪れることも多いがの土地家屋調査士ですが、その隣の家の方とトラブルが起きるというのは少なくないようです。
人によっては非協力的だったり少しでも得をしようとごねる方もいるらしく、そういった場面で精神的に疲れてしまう方もいます。
土地家屋調査士で「隣地は運次第」と言われるのは、人間関係が絡んでくるからのようです。
土地家屋調査士になるのはやめとけという声への反論
反論1】今やブラック労働が当たり前の業種ではない
近年では働き方改革も進み、ブラックと言われつつある調査士の業態にも変化が訪れつつあります。
就職や転職時にうまくホワイトな事務所を見つけることができれば、代休や育休を始めとした休暇の体制がしっかりと整っていることも多いそうです。
昔のようなきつい労働環境も変わりつつあることから、一概に「やめとけ」とするのは間違いと言えるのではないでしょうか。
反論2】研修や慣れで問題なく適用できるようになることが多い
土地家屋調査士は独立を目指す方が多いですが、ほとんどの方はまずどこかの事務所に所属して研修の期間に入ることになります。
その期間は誰でも0からのスタートで、一定期間の研鑽を積めば誰でも一線で活躍できる調査士に成長できるはずです。
弁護士や司法書士なども最初は法律事務所に所属するのが大多数のため、調査士に関しても新人教育が手厚い事務所に所属することが重要となっています。
反論3】独立・開業することで超高収入を目指せる
しっかりと事務所などで経験を積んで独立開業できれば、平均的な年収である500~600万円を大きく超える収入を狙うこともできます。
もちろん案件を獲得するための努力は必須ですが、成功できれば年収1,000万円以上も夢ではないという意見もあります。
知名度が低いために他業種と比較して競争が緩やかというのも魅力で、ぜひ皆さんのキャリアの選択肢に選んでみてはいかがでしょうか?
土地家屋調査士の仕事がない・仕事がなくなるって本当?
また「土地家屋調査士はやめとけ」に並んで見られる意見として、「土地家屋調査士の仕事がない」という声もあります。
「調査士の仕事がない」と主張される最大の理由は、景気の悪化によって不動産関連の取引が減少し活躍の場が減っているという状況です。
バブル期には頻繁に建物が取引され新しいビルが次々と立てられましたが、近年ではその動きも沈静化しています。
特に人口の大きな比率を占める高齢者の方は不動産の取引を行うことはあまりないため、「これから仕事が減っていくのではないか」と懸念している方が多く見られました。
上記のような主張は確かに正しいですが、一方で「調査士には新たに活躍できる場面も増えるのではないか」という声も多く聞こえます。
というのも今後団塊の世代が2022年から75歳と後期高齢者のフェーズに入るため、相続による土地の売買や分筆が増えることが予想されているのです。
また最近では市民の法リテラシーが高まったことで土地間での境界を定める依頼も増えていることから、土地家屋調査士の仕事がなくなるのは現実的な話ではないと言えるでしょう。
土地家屋調査士試験には独学で合格できる?
結論として、土地家屋調査士試験に独学で対策を行うのはおすすめできません。
不可能というわけではありませんが、必要とされる勉強時間は1,000時間~1,500時間とされる試験を前にすれば非常に非効率となってしまうのです。
教材選びから学習計画まで決めるのは、人によっては気が遠くなるような時間かかってしまうこともあります。
最速で合格を狙いたい方にとって、独学は到底最善手とは言えないのです。
独学では作図問題の対策が出来ない
試験概要で既に知っている方もいるかもしれませんが、土地家屋調査士試験では作図という記述式問題が課されます。
市販されているテキストはもちろんあるものの、初学者の方などでは理解が難しいことが多いようです。
また最新の試験トレンドや細かい注意点は書かれていないことが多く、独学は本当におすすめできません。
こういった問題点を全て排除できる勉強法こそが、通信講座なのです。
確実に合格を目指すなら通信講座
実際の試験では択一問題だけだはなく書式という製図の問題も出題されるため、独学での対策はほぼ難しいと言えます。
最適な参考書があまりない上に記述問題では高校数学の範囲の知識も必要となるため、効率よく対策を進めないと合格は難しいでしょう。
最近では受験勉強中の方や合格者の中で、お手頃な価格で初学者でも合格を目指せる通信講座を受講している方が増えているようです。
土地家屋調査士は他の士業に比べて、「独学で合格する人」はとても少ないです。参考書や学習テキストがあまり充実しておらず、一人で必要な情報量に触れることがなかなか難しいからです。なので初めて勉強される場合は、学習塾や通信講座に通うなどして効率よく学習を進めることが最短かもしれません!
— 土地家屋調査士キャリア支援@リーガルジョブボード (@LJBsurveyor) November 9, 2021
土地家屋調査士は知識・経験があれば好待遇を受けやすい
今回はインターネット上などで見られる、社会調査士への意見についてその真偽を調査しました。
もちろん土地家屋調査士は大変な仕事ですが、その強すぎる偏見は間違っているというのが結論です。
現在では様々な待遇が改善されている職場も多く、しっかりした知識と経験を積めば誰でも活躍できる職種といえます。